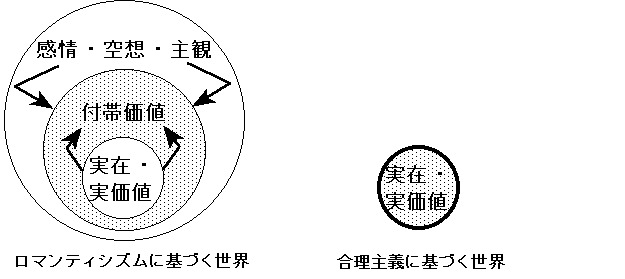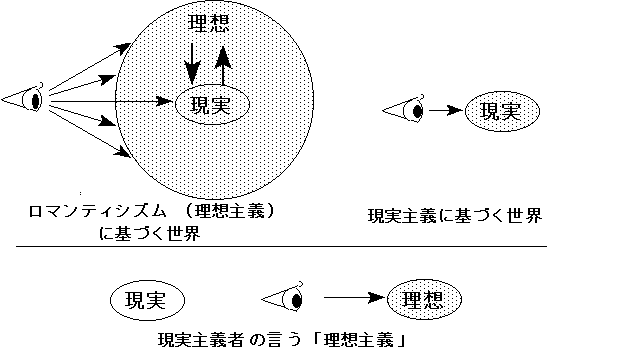| <2-8-7> | 「としみの脳味噌」(日米学生会議日本側参加者向けの会報に連載したエッセー集)より | |
|
Romanticismについて |
||
|
||
|
<僕はロマンティシストである> <花はなぜ咲くのか> しかし、高校生となった高野少年はこの「正解」に、ふと疑問を持つ。
世の中の全ての事象を「真理」という言葉で説明しようという科学者たちの試みはよく理解できるし、そこにまた科学の魅力はあるわけだが、この世の中はそう簡単に割り切れるものではないのである。 <ロマンティシズム×合理主義> つまり、科学の「真理」を生活のあらゆる面にあてはめ、「真理」の枠から外れる「無駄」を排除するのが合理主義、そして、その「無駄」に意味を見出すのがロマンティシズムであるという、きれいな構図ができ上がる。高校時代の僕は、「真理」の存在を認めつつ、「無駄」にも愛着を抱いていたのである。 <ロマンティシズム=付帯価値の追求> <ロマンティシズム=意味論> 科学が多様化・細分化・専門化する中で、近年、全体的な視点から科学の意味を考える科学者が脚光を浴びるようになっている。多田富雄氏、養老孟司氏、中村桂子氏などはその代表である。そして僕も、この「意味論」に大きな関心を抱いている。 46JASCの哲学分科会で僕は、「科学の普遍性追求には限界が見えてきており、これからの『人間性の時代』においては、科学も人間との関わりにおいて捉えるべきである」と述べた。人間の外側に純粋な系を作って、そこに普遍的真理を追求するのは、不可能かつ無意味であり、人間の脳を主体において、自然の事象を主観的に眺める方が有意義かつ面白いことだというのが僕の考え方なのである。そして、最近になって、この考え方の根底にあるのもまたロマンティシズムであるということに気付いた。 <ロマンティシズムと男と女> もちろんこれは、生物学的事実に過ぎないし、多田氏が洒落っぽく言っていることではあるが、これをジェンダーにあてはめて考えるというのも、悪くない発想であろう。例えば、養老孟司氏はこう言っている。「女性はそれ自体が『存在』であるからいいが、男性にはそれがなく、外からアイデンティティーを与えられなければならない。その結果できあがったのが男性中心社会なのではないか。」つまり、男はゲノムにない「存在感」を、社会における地位や権威で補ったというのである。 |
||
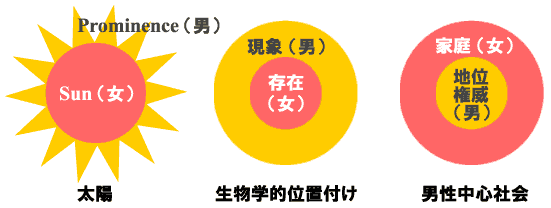 |
||
| 男はロマンティシストである。そして、そのロマンの対象は「女性」である場合が多い。「現象」が「存在」を拠り所として想いを寄せるというのは、実に明快な構図である。 それでは、女性は男性のどこに惹かれるのか。---こんなことを、男性の僕が書くのは気が引けるが、この章の流れに基づいて考えてみると、こういう結論になる。 「女性は、男性の『存在』ではなく、男性のもつ『付帯価値』に惹かれる。具体的に言えば、『強さ』や『優しさ』か、はたまた、『地位』や『権威』か。」 この結論に自信はない。あるわけがない。女心がわかっていれば苦労はない。 もし、女性でこの結論に異論のある方は、教えてくれるとありがたい。 <ロマンティシズムと芸術> 音とは、空気の振動であり、音の高さはその振動数で決まる。たとえば、Aの音は約440Hzである。また、ハーモニーというのは、振動数の倍率で決まる。(倍率が小さい整数の比で表せるほどきれいな響きになる。)たとえば、ドとレは8:9、ドとソは2:3であり、ドとソの方がきれいなハーモニーとなる。(ちなみに、1オクターブ離れた音は1:2の比になる。) <ロマンティシズムとモーツァルト> |
||
|
||
| それでも、僕はモーツァルトにはロマンティシズムがぴったりしていると思う。彼自身がロマンティシストであったというのは様々な文献からうかがえるし、専門家が「古典派」と位置づける彼の音楽にしても、「ロマン派」的な要素を感じる。同じ古典派に位置づけられる初期のベートーベンと比べてみると、ベートーベンが、いかにも形式張っているように感じるのに対して、モーツァルトの方にはそれが感じられない。モーツァルトの音楽がいわゆる「古典派」の形式を備え持っているのは確かであるが、ベートーベンが「形式」にあてはめて音楽を構築したとするならば、モーツァルトは、自分の思うままに作った曲が自然と「形式」にあてはまっていたと言うべきである。少なくとも、僕にはそう感じられる。 形式からの自由、そこがロマンティシズムの重要な点なのである。 <ロマンティシズム=形式からの自由> <ロマンティシズムは合理主義を包含する>
<ロマンティシズムと新興宗教> ヨーロッパでは、中世までカトリック教会が社会を支配し、「合理性=キリスト教・絶対神」という考えが、民衆にまで浸透していた。人々は、「実在」と、キリスト教によって与えられた「実価値」に頼るだけで、とりあえずは安心して生きることができたのである。 しかし、その後のカトリックの権威の失墜や、宗教の多様化、現在まで続く世界の混沌化などによって、「実価値」はゆらぎ始めた。日本でも、「家」制度の崩壊、封建制・天皇主権制の崩壊などが同様の事態をもたらした。「実価値」がゆらげば、人々は新たな「実価値」を求めるか、「付帯価値」の方に安定感を求めることになる。 この時、近代自我という「実価値」を手にした人は、「自我」を礎にして自己の世界を構築できたのだが、そういう「実価値」を手に入れられなかった人は、「実在」にも「実価値」にも基づかない「付帯価値」、いわば「浮遊価値」に安定感を求めることになった。近年、多くの人が新興宗教に傾倒しているが、「浮遊価値」にしか安定感を求められない人々の増加がその背景にあるように思う。僕は、「ロマンティシズム=付帯価値の追求」という定義をしているわけだが、「浮遊価値」の追求というのは、倒錯したロマンティシズムと言えるかもしれない。
<ロマンティシズム=理想主義>
ロマンティシズムについて、かなり美化して書いてきたが、やはり、上記の②の意味にも触れるべきだろう。 ロマンティシズムを好ましく思わない人がいるとすれば、その人は、おそらく、上記の「現実を逃避し」の点に引っかかっているはずである。僕は理想主義者であり、現実主義者の方々からは、よく「それは理想論じゃないか、君はもっと現実を見つめるべきだ。」という殺し文句を浴びる。今回はこの場を借りて、この言葉に反論を試みたいと思う。 まず、確認しておかなければならないのは、上記の広辞苑の定義は、現実主義者の見方だということである。僕の定義するロマンティシズムは、そもそも現実を逃避していない。現実とかけ離れた所に理想を抱き、それだけを追求する理想主義者もいるかもしれないが、そういう人は、僕でも批判するだろう。 僕の定義では、理想は現実を包含するものである。そして、この構図は、ロマンティシズムが合理主義を包含する構図と酷似している。 下の図を見ればわかるが、ロマンティシズムに基づく世界の方が、現実主義に基づく世界よりも遥かに広い。現実主義者は、現実しか見ることのできない「井の中の蛙」であるが、ロマンティシストは理想を基準にして物事を考えるので、それだけ広い視野を持つことになる。現実は理想世界の一つのオプションであり、もし、現実が優れたものであれば、現実を理想的なものとして選択することも可能である。よりよい世界を作るためには、より多くの選択肢があった方がいいわけで、たった一つの選択肢しか頭にない現実主義者よりも、無限の選択肢を考えうるロマンティシストの方が優れているのは明白である。
JASCの活動を通じて心強く思ったのは、現実をしっかりと見据えた上で、なお、理想を追求する人たちの存在である。安易に現実主義に流されてしまいがちな世の中だが、やはり、常によりよい世界の追求というのは忘れずにいたい。 第47回日米学生会議の総合テーマは、"Reflecting on the Past, Forging Our Future"「時代の創造 〜歴史に学び、理想の実現へ〜 」である。「理想」とは、「非現実」ではなく、「実現するもの」なのである。
<ロマンティシズムと夢> 僕の好きな言葉は、「夢は大きい方がいい。その分人生が大きくなる。」である。これは、上の図の「理想」を「夢」に置き換えて考えればわかりやすい。現実だけに生きるのではなく、外側に大きな夢の円を描いて、その実現を目指して人生を歩めば、世界も広がるのである。現実に満足していては進歩はない。 僕はいつまでも夢を追い続けていたいと思う。
<万人がロマンティシストである> 「僕はロマンティシストである」ということから書き始めたこのエッセイだが、思うに、人間とはみなロマンティシストである。人間とその他の動物の違いは、ロマンティシストであるか否かである、と言うこともできるかもしれない。人類は、言葉を手に入れたとき、同時にロマンティシズムも手に入れたのである。せっかくのこの財産、うまく使わなければもったいない。ロマンティシズムは、この世の中を豊かにするための道具なのである。
<参考文献> 「広辞苑 第三版」 新村出編 (岩波書店) 「免疫の意味論」 多田富雄著 (青土社) 「『私』はなぜ存在するか」 多田富雄・中村桂子・養老孟司著 (哲学書房) 「音楽の基礎」 芥川也寸志著 (岩波新書)
|
| [目次へ] |