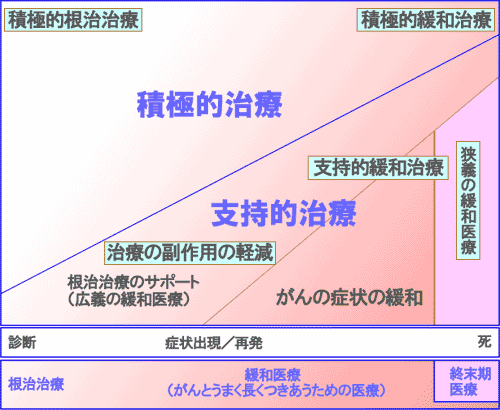表1に示したとおり、具体的ながんの治療法は、「積極的治療」と「支持的治療」に分類される。積極的治療とは、手術、抗癌剤、放射線治療など腫瘍を直接攻撃する治療で、一般に「がんの治療」と言われるのはこちらである。これに対し、支持的治療というのは、腫瘍には影響を与えないが、腫瘍や治療に伴う不快な症状を緩和させる治療のことである。がんとうまくつきあい、人間らしく日常生活を送るためには、なくてはならない治療法である。
積極的治療と支持的治療がバランスよく行われるのが理想の医療であるが、日本ではバランスがとれているとは言い難い状況にある。「一般病院-根治治療-積極的治療」「ホスピス-緩和医療-支持的治療」という棲み分けがなされ、両者は断絶している。
まずは、「根治治療至上主義」「緩和医療特殊論」にメスを入れたい。
根治治療こそが自分の使命だと思い込んでいる多くの医者は、積極的治療を徹底して行う。腫瘍を完全になくすために、体の一部を切り取り(手術)、放射線を浴びせ(放射線治療)、細胞を殺す物質を全身投与する(化学療法)。体の中にできた腫瘍を攻撃するのであるから、副作用や合併症は必発であるが、「癌と闘うのだから、副作用は我慢するのが当たり前」と言い放ち、副作用を和らげるための支持的治療にはあまり関心がない。一般病院では、こういう形で、根治治療としての積極的治療が次から次へと重ねられていき、それが限界に達すると、「もう打つ手がない」という言葉とともに見捨てられ、この瞬間、根治治療から緩和医療への切り替えが行われる。
かつては、打つ手がなくなったあとでも、根治治療の延長として苦痛を伴う延命治療が平気で行われてきたが、緩和医療という概念が広まってから、そういうことはなくなった。苦痛の時間だけを増やす延命治療の代わりに、最期の時間の苦痛を取り除く緩和医療が考慮されるようになってきたのである。しかし、緩和医療は、終末期という限られた状況の患者さんに対して、特別な場所(ホスピスなど)で行われる特殊な医療として認識され、がん医療体系を変えるほどの影響力はなかった。あくまでも、がん医療の主流は根治治療であり、「やれるところまでやって、それでもどうしようもなければ、敗北宣言して緩和医療へと患者さんを送り込む」というのが、多くの医者の抱いているイメージである。
早期がんに根治治療を行って根治が達成できれば、患者さんは幸福であろう。しかし、根治治療後に再発をきたしたり、発見時にすでに進行している場合、積極的治療をどんなに重ねても、腫瘍を完全になくすことができないというのが現実である。根治治療では、根治が勝利で、根治できないことは敗北であると考えられ、患者さんは、根治という達成しえない希望にすがって壮絶に闘い続けることになる。肉体的な苦しみの結果として、敗北が明らかになるというのは、絶望的なことではないだろうか。ある瞬間において、見せかけの希望が崩壊して絶望がもたらされ、そこで根治治療から緩和医療への切り替えが行われるとしたら、それは、健全な医療とは言えない。緩和医療を、敗北や絶望の医療としてしまう医療体系を改め、真の緩和医療を浸透させる必要がある。根治にこだわって不幸を増大させるのではなく、より早い時期から、ゆるやかに緩和医療へと考え方や治療方針を切り替えていき、バランスよく人間の幸福を目指していくべきである。
「根治治療-積極的治療」「緩和医療-支持的治療」という固定観念もバランスを欠いている。
根治治療においても、積極的治療だけでなく、積極的治療に伴う副作用を軽減させるための、支持的治療が重視されるべきであり、可能な限り苦しみを味わうことのないように治療が進められるべきである。「がんとうまくつきあう」だけでなく、「治療ともうまくつきあう」ことが求められ、これも広い意味での緩和医療と言える。世界保健機構(WHO)は、1990年に発行した報告書の中で、このように書いている。「緩和ケアは、病気の早期の段階から、抗腫瘍治療とともに用いられるべきである」。
また、緩和医療においては、支持的治療だけではなく、時には、積極的治療も用いられるべきである。手術、放射線治療、抗癌剤治療などの積極的治療は、適切に用いれば、症状緩和に有効である。根治を目指すわけではないので、つらい思いをして闘う必要はない。体にできるだけ優しい方法をとり、副作用よりも、症状の改善度の方が大きいと判断された場合に、初めて治療が行われる。治療対象は、腫瘍そのものではなく、症状であり、たとえば、症状のない腫瘍に対して、つらい副作用を我慢してまで治療を行うべきではない。
「根治ができないとしても、せめて延命を」というのが、多くの患者さんの切実な願いであろう。「緩和医療とは、命を延ばすことも、縮めることもしない医療である」という定義もあるが、私は、緩和医療が、人間の幸福を考える医療である以上、命の長さも考慮に入れるべきであると思う。もちろん、苦痛だけを増やすような延命ではなく、苦痛のない時間を増やすという延命である。「腫瘍とうまく長くつきあう」という目標にはそういう意味もこめられている。「延命治療では症状緩和が考慮されず、症状緩和を優先させれば延命はあきらめなければいけない」という誤解があるが、生命の量と質とは二者択一のものではなく、ともにバランスよく追求されるべきものである。実際、症状緩和を第一目標においた治療方針が、必ずしも延命と矛盾していないということが、いくつかの臨床試験で示されている。積極的治療の選択は単純にできるものではないが、「腫瘍とうまく長くつきあう」という目標に近づくために、何をどのように行うべきか、患者さんの人生観も考慮しながら、患者さんと主治医が納得できるまで話し合うべきである。
以上述べたことをまとめたのが図1である。診断後、根治治療が行われ、腫瘍の再発などで腫瘍をなくすことができないとわかったあとには、緩和医療へとゆるやかに移行していく。それに伴い、治療法の重点は、積極的治療から支持的治療へと移っていくが、そのどちらかが不要になるということはない。根治治療においても支持的治療は必要であり、緩和医療においても積極的治療は必要である。支持的治療は、「治療の副作用の軽減」と「がんの症状の緩和」という二つの役割があり、根治治療の際に行われる支持的治療は主に前者である。がんによる症状出現後は、症状緩和のための支持的治療のウエイトが大きくなる。症状緩和のためには積極的治療も有効であり、これは「積極的緩和医療」と位置づけられる。「狭義の緩和医療」とあるのは、余命がわずかであることが予想される場合に行われる症状緩和治療であり、いわゆる終末期医療と呼ばれるもので、ここに積極的治療は含まれない。私が緩和医療として定義しているのは、腫瘍をなくすことができないとわかったあとに行われる、「腫瘍とうまく長くつきあう」ための治療であり、「積極的緩和医療」と「支持的緩和医療」からなる。さらに、根治治療の際の支持的治療も含めたのが「広義の緩和医療」である。緩和医療の具体的な内容については、表2に示した。
このように、緩和医療というのは、がん医療のかなりの部分を占めることになるわけだが、大学の医学部では「緩和医療学」が教えられることはなく、ただひたすら根治治療の方法だけがたたきこまれている。そして、医療現場では、緩和医療は「狭義の緩和医療」としてしか捉えられず、「緩和医療はホスピスの仕事。一般病院はがんを治すためにあるのだから、緩和医療なんてやっていられない」なんてことが言われたりする。がんというものを今一度見つめ直し、がん医療の目的を見定め、真の緩和医療をより広く浸透させる必要がある。緩和医療とは、人間の幸福のための医療であり、がん医療のすべての場面において、適切に用いられるべきである。
|